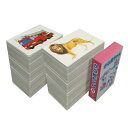はじめに

「子どもの勉強を楽しく、効率よく進めたい」と考える親御さんは多いはず。
そんな方におすすめなのが、フラッシュカード学習です。
本記事では、初心者の方でも自信を持って実践できるフラッシュカードのやり方を紹介します。
紙とアプリの違いや効果的な使い方、自作のコツまで詳しく解説しています。
本記事は以下の方におすすめです。
- フラッシュカードってどんなメリットがあるの?やり方なども知りたい。
- フラッシュカードのおすすめ商品について知りたい。
- 実際にフラッシュカードを使用している人の感想が聞きたい。

まちなも息子が生後3か月になってから始めました!

我が家で使用しているのは『七田式』!実際に使用感も交えて紹介していくよ~
フラッシュカードとは?基本から学ぼう

フラッシュカードとは、表に質問、裏に答えを書くカード型教材のこと。
語彙や英単語、計算式などの暗記に向いており、短時間で反復学習が可能です。
教育現場では幼児教育から中学受験対策まで、幅広く活用されています。
カードを素早く見せることで、脳の瞬発力や集中力も鍛えられるのが魅力です。
フラッシュカードの効果的な使い方・めくり方

初心者でもできる!基本のやり方
1日10〜15分程度を目安に、1回に使うカードは20〜30枚以内が理想です。
テンポよく読み上げ、わからないカードは繰り返し出すのがポイント。
1週間程度同じカードでフラッシュしたら、半分を入れ替えて新しいカードにしていきます。

入れ替えるのは半分というのがポイント!半分は見たことあるカードを残すことでやる気をそがないようにします。
フラッシュカードは1秒で1枚スピーディにめくっていくことがポイントです。お子さんとトライする前に素早くめくれるように練習してみましょう。うまくめくるために指サックなどを使用するのもポイントです!
親の関わりが大切
子どもが答えられたらすかさず褒めることでモチベーションがアップします。
声かけやジェスチャーも取り入れると、楽しく続けられます。
記憶に残りやすいフラッシュカードのやり方・作り方
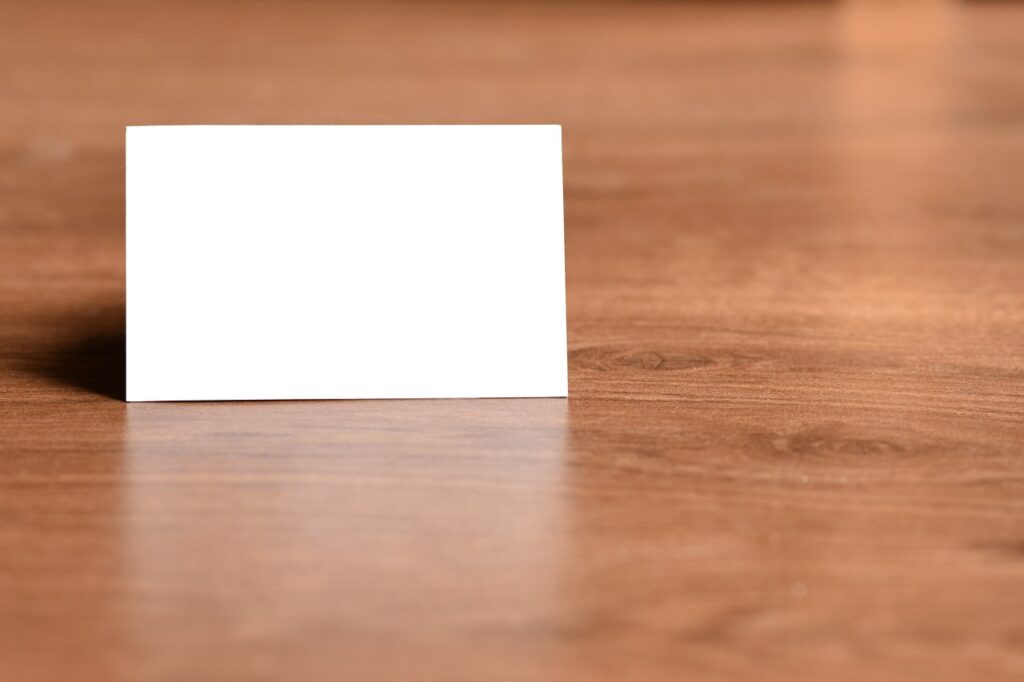
記憶に残すには、情報をシンプルに整理してカード化するのが基本です。
自作する場合は、1枚に1つの情報を載せ、文字数もできるだけ少なくしましょう。
例:英単語カード
- 表:apple
- 裏:りんごの絵+日本語「りんご」
イラストを使うと視覚情報が記憶に残りやすくなります。
忘却曲線を活かした復習スケジュール
人は1日後には約70%を忘れると言われています。
1日後・3日後・1週間後・1か月後に復習することで記憶が定着します。
紙とアプリ、どちらがいい?それぞれのメリット・デメリット
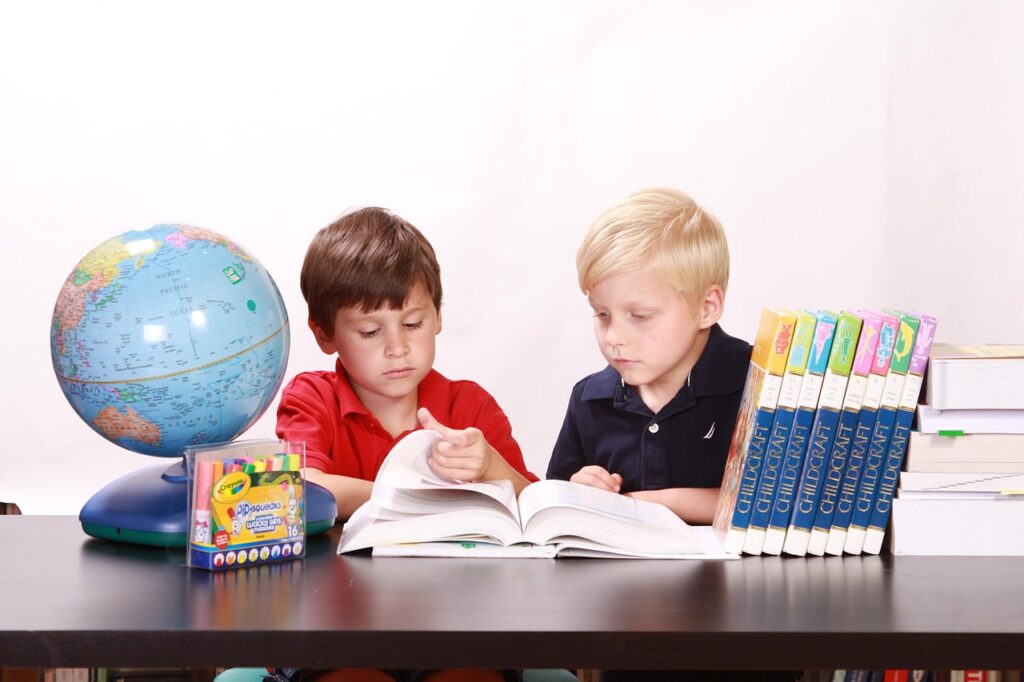
紙のカードの特徴とメリット
- 手でめくる感覚があり、記憶に残りやすい
- オリジナルカードを作りやすい
- 目に優しく、集中しやすい
おすすめ:七田式、くもん出版などの市販カード

本格的に取り組みたい方は『七田式』、お試しで使用してみたい方は『くもん』がおすすめです!

まちなは最初から、本格的に取り組んでフラッシュカードについてレビューしてみたいと思ったので『七田式』を購入いたしました!
アプリの特徴とメリット
- スマホ1台でいつでも学習できる
- 自動で復習スケジュールを管理してくれる
- 音声や画像を簡単に組み込める
おすすめアプリ:Anki、Quizlet、MemoryHelper
両方の使い分けがおすすめ
家では紙、外出先ではアプリと、シーンごとに使い分けるのが理想的です。
フラッシュカード選びに迷ったときのチェックポイント

フラッシュカード選びで迷ったら、まずは目的と子どもの学年に合っているかを確認しましょう。
自作は内容を自由に調整できますが、時間と手間がかかります。
忙しい方には、すぐに使える市販のカード(七田式・くもんなど)がおすすめです。
また、視覚的に覚えるタイプが向いている子には、イラスト入りカードが効果的です。
SNSや育児ブログでのレビューも参考になります。
実際の使用感や年齢別の評価を見ることで、失敗のない選択ができますよ。
〈レビュー〉七田式のフラッシュカードを使用してみて・・・
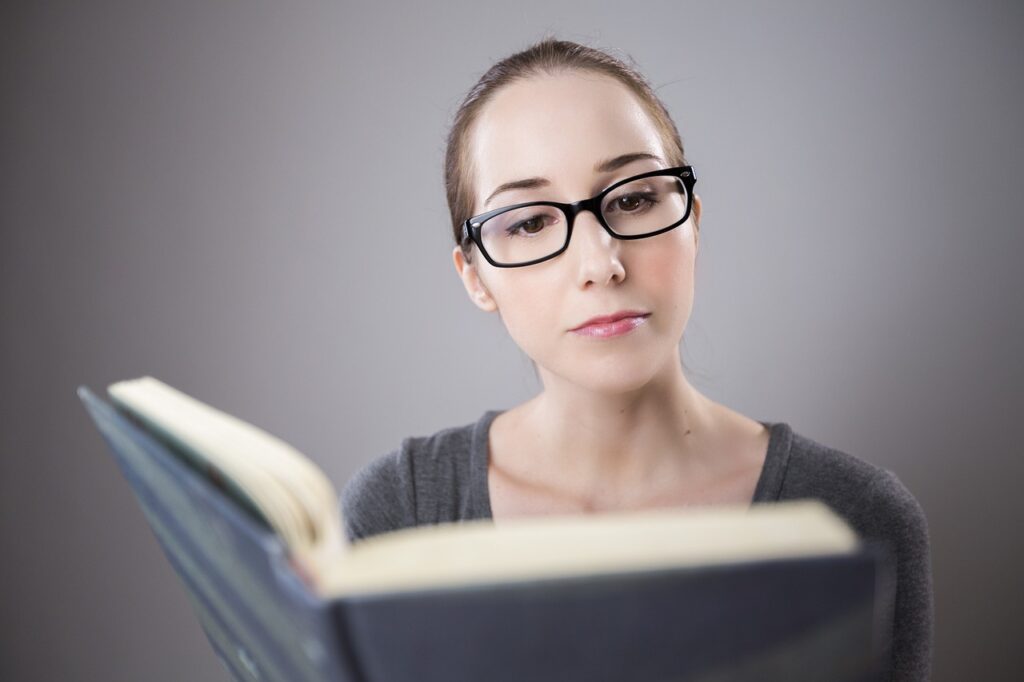
我が家では七田式の『かな絵ちゃん』シリーズのフラッシュカードを生後3か月の頃から使用しています。七田式のフラッシュカードは一枚が分厚くかなりフラッシュしやすいです。またフラッシュ台も付属しており、フラッシュがどうしても苦手な人は台に置きながらフラッシュが可能です。
まちなは使用中は以下のことに気をつけています。
- バウンサー等に座らせてある程度、集中して見れる角度にする
- 泣いて嫌がった場合は、無理してやらなくてOK
- 集中して見ていない日があったとしても、耳だけ聞いていればOK
- フラッシュカードを行う前後で、ハグなどの愛情表現をたくさんする
使用枚数は、午前中と午後に分けてフラッシュしていて全部で30枚ほどフラッシュしています。またフラッシュカードと合わせて、ドッツカードも同じ時間で実践しています。
じっと集中して見てくれることが多く、一つの遊びとして楽しんでいます。もう少し継続してみて、効果などを追ってレビューしていきたいと思います!
より効果を高めるための応用テクニック

覚えにくい内容は絵や色で補強
難しい用語や数字は、イラストやカラーペンを使って印象付けるのが効果的です。
他の学習法との組み合わせ
マインドマップやノートまとめと併用することで、理解力と記憶力の両方を鍛えられます。またカードを外出時などにもっていき、実物を合わせて見せてあげることで更に経験がつまれます。
家族との学習で楽しさアップ
兄弟や親子でクイズ形式にすると、遊びながら学習できます。
「どっちが多く正解できるかな?」などの工夫もおすすめです。
<まとめ>目的をもって楽しく実践すれば、誰でも効果を出せる!

フラッシュカードは、やり方を工夫すれば誰でも楽しく、効果的に学べる学習法です。
まずは目的に合わせて、市販カードやアプリを選び、今日から始めてみましょう。
「勉強=苦手」ではなく、「勉強=楽しい」に変わるきっかけになるはずです。
親子で学びの時間を共有しながら、子どもの成長を一緒にサポートしていきましょう!